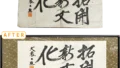先日のことですが、阿刀田高さんの『やさしいダンテ』を拝読しました。ダンテ・アリギエーリは13世紀の詩人で、『神曲』において死後の世界を描いたことで有名な人物です。これがなかなかに難解な作品で……。先にお断りしておくと、あくまでも「阿刀田さんの書籍を読んで私が感じたこと」を述べているだけであり、宗教的な正誤を論じるつもりは一切ございませんので、ご了承ください。
さて、私は仏教徒です(といっても、そこまで熱心ではないのですが……)。仏教にはさまざまな神様がいらっしゃいます。大日如来、薬師如来、そして大黒天や毘沙門天など。如来と天の違いについてはここでは割愛しますが、要するに仏教は多神教ですよね。そして、日本では仏教の神々とは別に、八百万の神々も広く敬われています。これが日本人の宗教観に深く根付いていると思うのです。
学生時代に経験したことですが、この「多神教的な価値観」は一神教の方とはなかなか相容れないことが多いようです。例えば、木や水の神様を信仰することについて、「お前は神様が作ったものを、神様として崇めているのか?」といった議論になることがあります。一神教の方の信仰の深さにもさまざまな段階があるでしょうが、考え方の根本が異なるのだなと改めて感じたものです。
この点において、『神曲』の中でダンテが描く世界は非常に興味深いものでした。一神教の価値観のもとにある物語でありながら、ローマやギリシャの神々が登場するのです。これがキリスト教的価値観と矛盾しないのか? という疑問が湧きました。ただ、ローマやギリシャは元々多神教文化を持つ地域であり、その変遷の途中にキリスト教が発展したと考えると、それほど不思議ではないのかもしれません。
そして、この後に花開くのがルネサンス文化です。例えば、ミケランジェロの『最後の審判』は、キリスト教の世界観を色濃く反映した作品ですが、同時期にボッティチェッリは『ヴィーナスの誕生』を描きました。こちらはギリシャ神話の女神アプロディーテー(ローマ神話ではヴィーナス)を描いた作品です。
『ヴィーナスの誕生』は、海から生まれたヴィーナスが貝殻に乗って舞い降りるシーンを描いています。西洋美術の中でも特に優雅で、繊細な線の美しさが際立つ作品ですよね。ルネサンス期にキリスト教世界の中でこうした異教の神話をモチーフにした作品が生まれたのは、当時の人々が古典文化に回帰し、人間の美しさや自然の神秘を再評価したからでしょう。
こうした芸術作品を目にすると、時間的・金銭的に余裕ができたら、ぜひヨーロッパへ行って実物を見たいなと思います。美術館で作品を鑑賞するのはもちろん、背景にある歴史や文化を深く知ることで、より一層楽しめるのではないでしょうか。
そして、私たちの暮らしの中でも、こうした芸術を取り入れることで空間に彩りを加えることができます。ボッティチェッリのような優美な曲線美を感じる作品を飾るのも素敵ですし、掛け軸や額装された絵画を取り入れることで、日常の中にアートのある暮らしを楽しむことができます。
サンコー商事では、美術品の修復や表装を通して、そんな「絵と暮らす」文化を提案しています。もし大切な絵画や掛け軸をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
📖 阿刀田高『やさしいダンテ』 🔗 KADOKAWA公式サイト
🎨 掛け軸・額装・美術品修復のご相談はこちら👇 🔗 サンコー商事 公式サイト